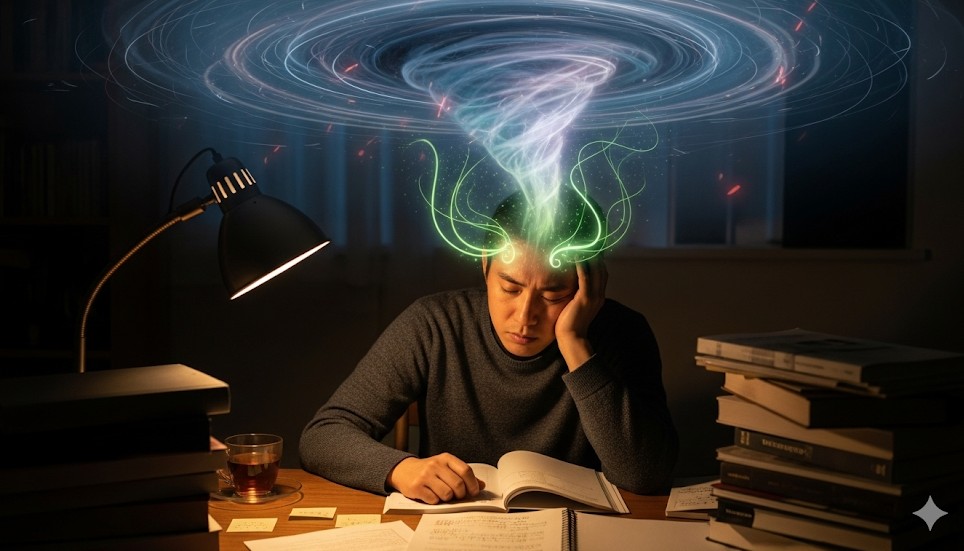本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています
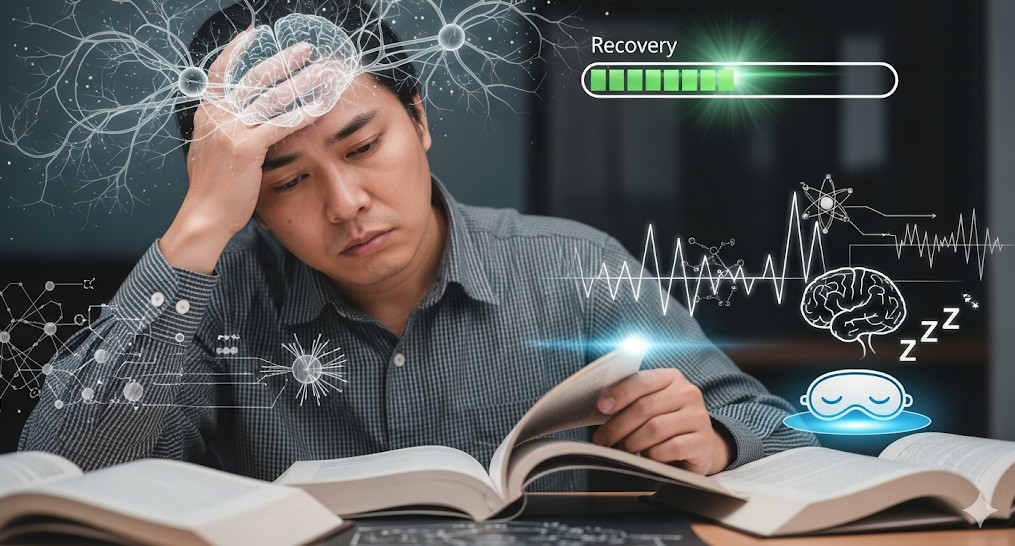
現代社会において、多くの情報に囲まれる中で「読書」は心を落ち着かせ、知識を深める貴重な時間です。
しかし、好きなはずの読書なのに、なぜか疲れる、内容が頭に入らずしんどいと感じることはありませんか。
また、資格取得など勉強のために読書をしても、脳疲労で集中力が続かないという悩みも聞かれます。
中には、寝る前の読書がよくないという話を聞き、リラックスのつもりが逆効果になっていないか心配になる方もいるでしょう。
さらに、疲れているのに休み方がわからない状態が続くと、読書が自律神経失調症につながるのではないかと不安に感じるかもしれません。
この記事では、読書で脳疲労が起きるのはなぜかという根本的な原因から、科学的根拠に基づいた脳疲労の回復法までを網羅的に解説します。
脳疲労対策として注目される瞑想の効果や、読書との上手な付き合い方を知ることで、あなたの読書体験はより豊かで快適なものになるはずです。
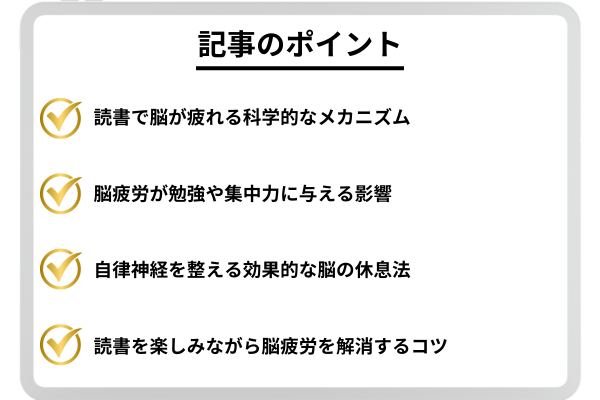
読書による脳疲労のメカニズムとは
この章では、読書によって脳が疲労する根本的な原因や、それが心身に与える影響について、科学的な視点から掘り下げていきます。
- そもそも読書で疲れるのはなぜなのか?
- 読書がしんどいと感じる脳の仕組み
- 脳疲労が勉強のパフォーマンスを落とす
- 読書と自律神経失調症の意外な関係
- 寝る前読書がよくないと言われる根拠
- 集中力を高める効果的な休憩の取り方
そもそも読書で疲れるのはなぜなのか?

読書をすると疲労を感じる主な理由は、脳が膨大なエネルギーを消費する活動だからです。
脳は体重の約2%の重さしかありませんが、体全体の消費エネルギーのうち約20%を使用する大食漢の臓器と考えられています。
そして、このエネルギー消費の大部分は、私たちが意識的に活動していない時にも発生します。
この無意識の活動を支えているのが「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる脳回路です。
自動車が停車中でもエンジンがかかっている「アイドリング」状態をイメージすると分かりやすいかもしれません。
DMNは、過去の記憶を整理したり、未来の計画を立てたりと、私たちが「ぼーっとしている」間も活発に働いており、脳のエネルギーの60~80%を消費するとも言われています。
読書は、このDMNの活動に加えて、文字情報を理解し、情景を想像し、内容を記憶するという、非常に高度で能動的な精神活動を要求します。
特に、物語の登場人物に感情移入したり、複雑な情報を整理したりする際には、前頭葉や側頭葉、海馬といった脳の様々な領域が活性化します。
このように、読書中は脳が通常時以上にエネルギーを消費するため、長時間続けると疲労を感じるのは自然な現象と言えます。
つまり、読書による疲れは、脳がしっかりと働いている証拠でもあるのです。
読書がしんどいと感じる脳の仕組み
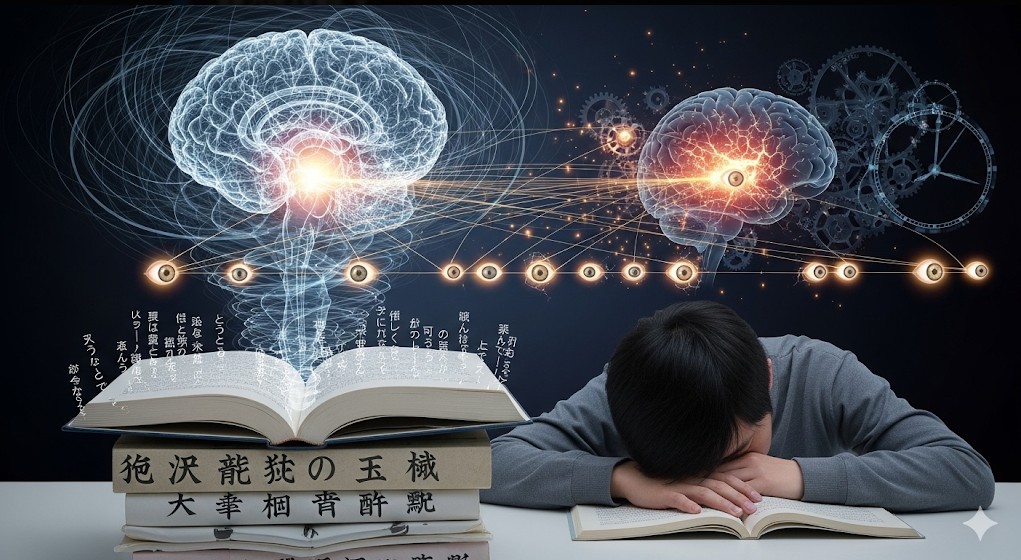
読書が単なる疲れを超えて「しんどい」と感じる背景には、現代社会特有の情報過多による「脳疲労」が関係しています。
脳疲労とは、脳が処理能力を超えるほどの情報にさらされ続けることで、正常な機能が維持できなくなる状態を指します。
人間の脳は、思考や理性を司る「大脳新皮質」と、感情や本能を司る「大脳辺縁系」がバランスを取りながら機能しています。
しかし、スマートフォンやPCから絶え間なく情報が流れ込んでくると、脳は常に情報を処理し続けなければならず、このバランスが崩れてしまいます。
情報が多すぎるにもかかわらず、それを整理したり活用したりするアウトプットが不足すると、脳は「情報メタボ」とも呼べる状態に陥ります。
この状態が続くと、大脳辺縁系の機能不全が起こり、それが大脳新皮質にも影響を及ぼすと考えられています。
その結果、思考力や集中力、記憶力の低下といった症状が現れ、本を読んでも内容が頭に入ってこない、文章を追うこと自体が苦痛に感じるといった「しんどさ」につながるのです。
本来、リフレッシュになるはずの読書が、情報処理で疲弊した脳にとってはさらなる負担となり、結果として「しんどい」という感覚を引き起こしている可能性があります。
脳疲労が勉強のパフォーマンスを落とす
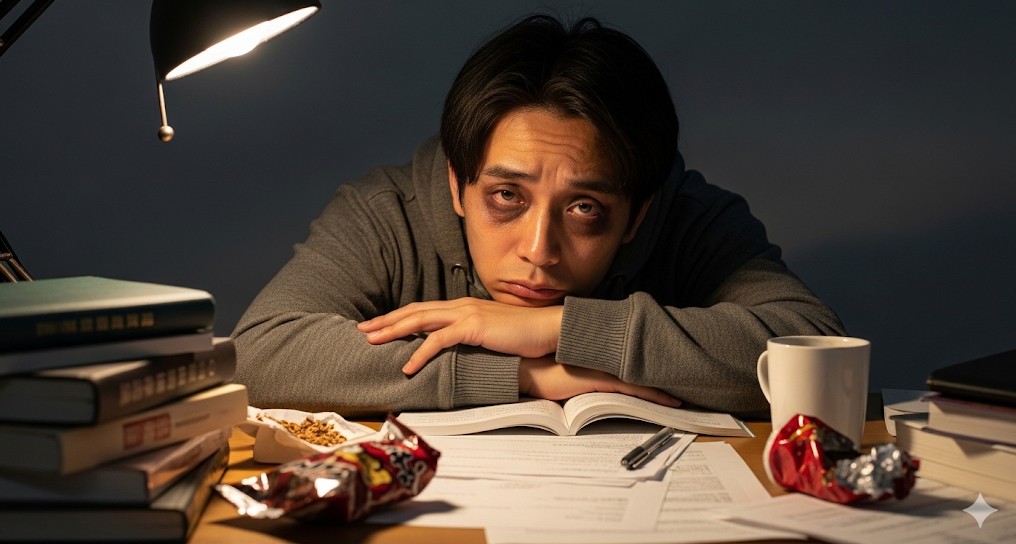
脳疲労は、勉強や仕事のパフォーマンスに直接的な悪影響を及ぼします。
資格取得やスキルアップのために読書で勉強しようとしても、脳が疲労した状態では、その効果は著しく低下してしまいます。
なぜなら、脳疲労は思考力や集中力だけでなく、記憶を定着させるプロセスにも深刻な影響を与えるからです。
何かを記憶するためには、まず対象に「集中」し、その情報を一時的に保持する「作業記憶(ワーキングメモリ)」に取り込む必要があります。
そして、脳がその情報を重要だと判断して初めて、長期的な記憶として定着させるプロセスが始まります。
しかし、脳が疲労している状態、特にスマートフォンなどで常に情報を受け続けている状態では、このプロセスが妨げられます。
脳は次から次へと入ってくる情報を処理することに手一杯になり、新しい長期記憶を形成するための余裕がなくなってしまうのです。
その結果、読んだ内容を覚えられず、同じ箇所を何度も読み返すことになり、勉強の効率が著しく低下します。
このように、脳疲労はインプットの質を下げ、知識の定着を妨げるため、勉強のパフォーマンスを大きく落とす原因となります。
効果的な学習のためには、まず脳を適切に休ませ、情報を処理できる状態に整えることが不可欠です。
読書と自律神経失調症の意外な関係

脳疲労は、精神的なパフォーマンスの低下だけでなく、身体的な不調を引き起こす可能性も指摘されています。
その鍵を握るのが、脳の中心部に位置する「間脳」です。
間脳は、私たちの意思とは関係なく心臓や内臓の働きをコントロールする「自律神経」の中枢を司っています。
前述の通り、情報過多によって大脳新皮質や大脳辺縁系のバランスが崩れると、その影響は隣接する間脳にも及びます。
間脳の機能が不全に陥ると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の2つから成り立っていますが、この切り替えがうまくいかなくなるのです。
その結果、常に緊張状態が続いたり、逆に無気力になったりと、心身のコントロールが効かなくなります。
具体的には、不眠、動悸、めまい、感情の不安定、食欲不振または過食といった、自律神経失調症に見られる様々な症状が現れることがあります。
読書自体が直接の原因ではありませんが、情報処理による脳疲労を放置したまま読書を続けることで、知らず知らずのうちに脳への負担が蓄積し、間接的に自律神経の乱れを助長してしまう可能性は否定できません。
心身の健康を保つためには、読書を楽しむ時間と同じくらい、脳を意識的に休ませる時間が大切になります。
寝る前読書がよくないと言われる根拠
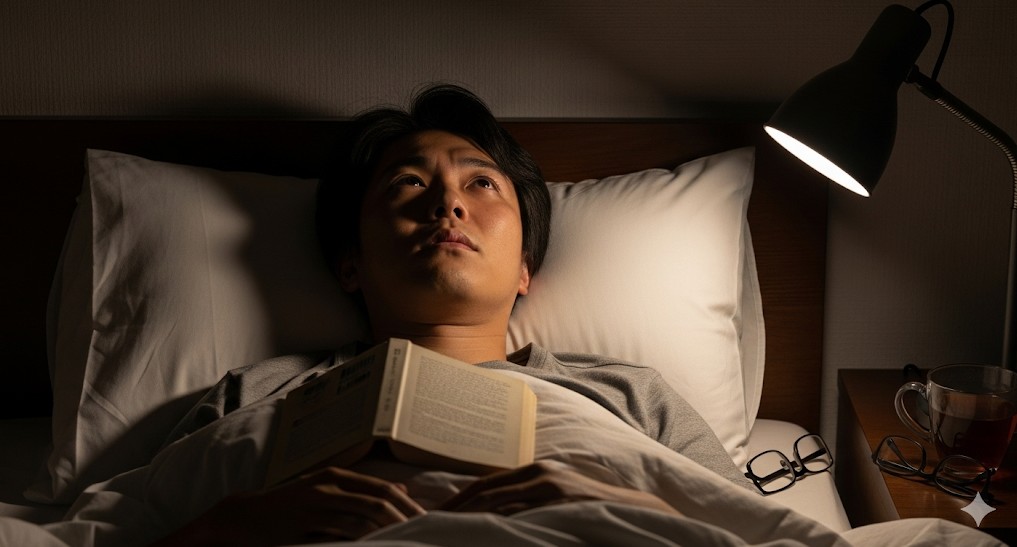
「寝る前の読書」には、リラックス効果がある一方で、睡眠の質を低下させる可能性があるため、「よくない」と言われることがあります。
その効果は、読書の方法や読む本の内容によって大きく変わるため、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。
寝る前読書のメリット
英国サセックス大学の研究によれば、読書はわずか6分間でストレスレベルを約68%も低下させる効果があるとされています。
物語に没入することで、日中の悩みやストレスから意識が離れ、心拍数が落ち着き、筋肉の緊張がほぐれます。
これにより、心身がリラックスし、副交感神経が優位になるため、自然な眠りに入りやすくなります。
寝る前読書のデメリットと注意点
問題となるのは、主にスマートフォンやタブレットなどの電子書籍で読書をする場合です。
これらのデバイスが発するブルーライトは、太陽光に近い性質を持つため、脳が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまいます。
その結果、眠りを促すホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりする原因となります。
また、紙の書籍であっても、サスペンスやホラーなど、読者を興奮させる内容の本は交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまう可能性があります。
リラックス目的であれば、穏やかな内容のエッセイや詩集、自己啓発書などが適していると考えられます。
| 媒体 | メリット | デメリット・注意点 |
| 紙の書籍 | ・ブルーライトの心配がない<br>・集中しやすく、リラックス効果が高い | ・内容によっては脳が興奮状態になる<br>・照明が暗すぎると目に負担がかかる |
| 電子書籍 | ・暗い場所でも読める<br>・多くの本を持ち運べる | ・ブルーライトが睡眠の質を低下させる<br>・通知などで集中が途切れやすい |
以上の点から、寝る前に読書をする際は、ブルーライトを発しない紙の書籍を選び、心を落ち着かせる内容の本を、暖色系の穏やかな照明の下で楽しむのが最も良い方法と言えるでしょう。
集中力を高める効果的な休憩の取り方

読書や勉強中に脳疲労を防ぎ、集中力を維持するためには、意識的に休憩を取り入れることが極めて有効です。
長時間連続して作業を続けるよりも、短い休憩を挟む方が、結果的に脳のパフォーマンスを高めることができます。
効果的な方法の一つとして、「25分間の集中と5分間の休憩」を1セットとして繰り返すというものがあります。
これは「ポモドーロ・テクニック」としても知られる時間管理術で、読書にも応用できます。25分という時間は、人間が深い集中を保ちやすい長さとされており、このサイクルを繰り返すことで、脳の疲労が蓄積するのを防ぎます。
休憩時間には、読書から完全に離れることがポイントです。スマートフォンをチェックするのではなく、以下のような活動を取り入れると、より効果的に脳をリフレッシュさせることができます。
休憩中におすすめの活動
- 軽いストレッチや運動: 長時間同じ姿勢でいると血流が悪くなり、疲労の原因となります。立ち上がって背筋を伸ばしたり、肩を回したりするだけでも効果があります。
- 窓の外を眺める: 遠くの景色をぼんやりと見ることで、酷使していた目の筋肉を休ませることができます。
- 水分補給: 脳の働きの多くは水分を必要とします。コーヒーや紅茶も良いですが、水やお茶で水分を補給することも大切です。
- 目を閉じて休む: 照明やモニターの光から目を解放し、数分間静かに過ごすだけでも、脳の情報処理を一時的に中断させ、リラックスを促します。
これらの短い休憩を計画的に取り入れることで、脳は過度な負荷から解放され、次の集中時間に向けてリフレッシュできます。
読書を始める前にタイマーをセットするなど、休憩を習慣化することが、脳疲労を防ぎながら集中力を高める鍵となります。
読書で脳疲労を解消する科学的アプローチ
この章では、蓄積してしまった脳の疲れを解消し、読書をより楽しむための具体的な方法について解説します。
科学的根拠に基づいた休息法や、新しい読書のスタイルを取り入れることで、心身ともにリフレッシュを目指しましょう。
- 疲れているのに休み方がわからない方へ
- 専門家が推奨する脳疲労の回復メソッド
- 脳疲労に瞑想がもたらすリラックス効果
- 新しい視点や発見があるオンライン読書会
- まとめ:読書による脳疲労との向き合い方
疲れているのに休み方がわからない方へ

「しっかり休んでいるはずなのに、なぜか疲れが取れない」と感じる場合、その原因は「休息の質」にあるかもしれません。
多くの人は「休息=体を動かさずに、何もしないこと」だと考えがちです。
しかし、前述の通り、私たちの脳は何もしていなくても「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」によってエネルギーを消費し続けています。
つまり、ソファでぼーっと過ごしていても、脳内では過去の失敗を悔やんだり、未来の不安を考えたりと、無意識の思考が駆け巡り、脳は休まるどころか疲労を蓄積させている可能性があるのです。これが、「体を休めても脳は疲れる」という現象の正体です。
本当に質の高い休息を得るためには、このような脳の「自動操縦」状態から意識的に離れ、「能動的な休息」を取り入れる必要があります。
能動的な休息とは、脳の雑念を払い、意識を「今、ここ」に集中させることで、DMNの過剰な活動を鎮めるアプローチを指します。
この状態を作り出す代表的な方法が、次項で解説する「瞑想」や「マインドフルネス」です。
疲れているのにどう休めば良いかわからないと感じたら、まずは「何もしない」休息から、「脳を意識的に休ませる」休息へと、考え方を切り替えてみることが、脳疲労からの回復の第一歩となります。
専門家が推奨する脳疲労の回復メソッド

脳疲労を効果的に回復させるためには、脳科学に基づいた様々なアプローチが存在します。
日常生活に手軽に取り入れられるものも多いため、自分に合った方法を試してみることをお勧めします。
食事によるアプローチ
脳の疲労回復に役立つ成分として「イミダゾールジペプチド(通称イミダペプチド)」が注目されています。
渡り鳥が数千キロも飛び続けられる力の源とも言われるこの成分は、高い抗酸化作用を持ち、脳細胞の酸化ストレスを軽減する働きがあるとされています。
公式サイトなどによると、鶏の胸肉やマグロ、カツオなどに多く含まれているとの情報があります。
読書法の工夫
いつもと違う本の読み方を試すことも、脳に新たな刺激を与え、疲労感を軽減するのに役立つ場合があります。
例えば、ミステリー小説などをあえて結末から読んでみる方法です。
物語のゴールが分かっている安心感から、脳内でエンドルフィンなどの快感物質が分泌されやすくなり、疲れを感じにくくなる可能性があると言われています。
ただし、これは一時的な対策であり、根本的な疲労回復には適切な休憩が不可欠です。
環境を整える
読書をする環境を見直すことも大切です。自分が最もリラックスできる静かな場所を選び、心地よい椅子や照明を用意するだけで、心身の負担は大きく変わります。
また、視覚的な情報処理に疲れた場合は、「オーディオブック」を活用するのも一つの手です。
「耳で聴く読書」は、目や体を休めながら物語や知識に触れることができ、脳の異なる部分を使うため、良い気分転換になります。
これらのメソッドを組み合わせ、自分の体調や気分に合わせて取り入れることで、読書による脳疲労を和らげ、より快適な読書時間を過ごすことができるようになります。
脳疲労に瞑想がもたらすリラックス効果

脳疲労の回復法として、近年科学的な注目を最も集めているのが「瞑想」、特に「マインドフルネス瞑想」です。
これは宗教的な修行とは一線を画し、脳を休息させ、集中力を高めるための科学的なトレーニングとして、多くの企業や教育機関で導入されています。
瞑想が脳疲労に効果的な最大の理由は、脳のエネルギー消費の大部分を占める「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」の過剰な活動を鎮めることができるからです。
瞑想では、自分の呼吸や身体の感覚に意識を集中させます。これにより、過去や未来へとさまよいがちな意識を「今、この瞬間」に引き戻し、雑念の連鎖を断ち切ることができます。
このプロセスを通じて、脳にはいくつかの良い変化が起こることが分かっています。
- α(アルファ)波の活性化: 瞑想中は、リラックス状態を示すα波が脳内で増加します。これにより、心の興奮が静まり、穏やかで安定した精神状態がもたらされます。
- ストレスホルモンの低減: 瞑想を習慣にすることで、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが低下することが多くの研究で示されています。
- セロトニン・エンドルフィンの増加: 気分を高揚させ、幸福感をもたらすセロトニンや、痛みを和らげる作用のあるエンドルフィンといった神経伝達物質の分泌が促進されると言われています。
静かな場所で楽な姿勢をとり、目を閉じて、ただ自分の呼吸に意識を向ける。
雑念が浮かんできたら、それに気づいて、またそっと呼吸に意識を戻す。
これを1日数分から始めるだけでも、脳はクリアになり、情報処理能力や集中力が回復する効果が期待できます。
瞑想は、脳にとって最高の休息法の一つと言えるでしょう。
新しい視点や発見があるオンライン読書会

一人で静かに本を読む時間は貴重ですが、時にその体験を他者と共有することで、読書はより能動的で豊かな活動に変わります。
特に、脳が疲れていて一人では読書がしんどいと感じる時に、「オンライン読書会」への参加は、新たな刺激とモチベーションを与えてくれます。
オンライン読書会は、専門的な研究会のような堅苦しいものではなく、本を介したカジュアルな交流の場であることがほとんどです。
参加するメリットは多岐にわたります。
思いがけない本との出会い
自分一人で本を選んでいると、どうしても興味の範囲が偏りがちです。
読書会では、他のおすすめ本に触れる機会が多く、これまで手に取ったことのないジャンルの魅力に気づかされることがあります。
知識の偏りをなくし、多様な視点を得るきっかけになります。
新たな視点の獲得
同じ本を読んでも、感じ方や心に残る箇所は人それぞれです。
他の参加者の感想や解釈を聞くことで、「そんな見方があったのか」と驚かされ、物語やテーマへの理解が格段に深まります。
これにより、物事を多角的に捉える力が養われます。
読書が能動的になる
「後で感想を共有する」という目的を持つことで、読書は単なる情報の受け取り(受動的)から、本質を掴み、自分の言葉で表現しようとする(能動的)行為へと変化します。
この意識の変化が、読解力を高め、内容をより深く記憶に定着させる助けとなります。
最近では「本を事前に読まずに参加できる読書会」も増えています。
例えば、日本最大級の読書会コミュニティ「リードフォーアクション」では、その場で本を読み、短時間で要点をつかむワークショップ形式が採用されており、忙しい人でも気軽に参加できます。
一人での読書に疲れを感じたら、このようなコミュニティに参加してみるのも、脳を活性化させ、読書の楽しみを再発見する良い方法です。
まとめ:読書による脳疲労との向き合い方
この記事では、読書による脳疲労の原因から、科学的な回復法までを詳しく解説しました。最後に、読書と脳疲労に上手に付き合っていくための重要なポイントをまとめます。
- 読書は脳の様々な領域を活性化させる高度な精神活動である
- 脳は意識していない時もエネルギーを消費し続けている
- 情報過多な現代社会では脳が疲労しやすい状態にある
- 脳疲労は集中力、記憶力、思考力の低下を引き起こす
- 脳の疲れは自律神経の乱れにつながる可能性がある
- 寝る前の電子書籍はブルーライトが睡眠の質を下げる
- 寝る前は穏やかな内容の紙の本を暖色系の照明で読むのが理想
- 25分集中して5分休むなど計画的な休憩が集中力を維持する
- 体を休めても脳は活動しており、能動的な休息が必要
- 脳の休息には意識を「今」に向ける瞑想が効果的
- 瞑想はストレスホルモンを減少させリラックスを促す
- 鶏胸肉などに含まれる成分が脳疲労回復に役立つとされる
- オーディオブックは目や体を休めながら読書を楽しめる
- オンライン読書会は新たな視点を得て読書を能動的にする
- 自分に合った休息法を見つけ読書と上手に付き合うことが大切
おすすめ記事